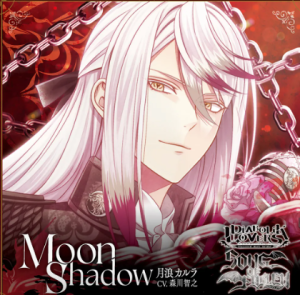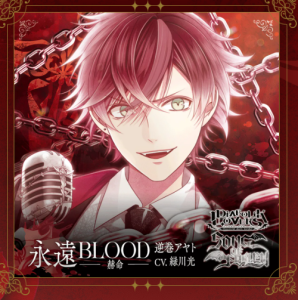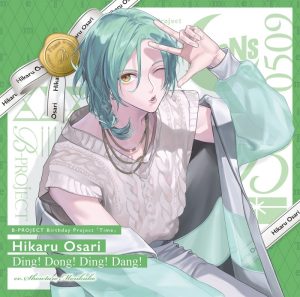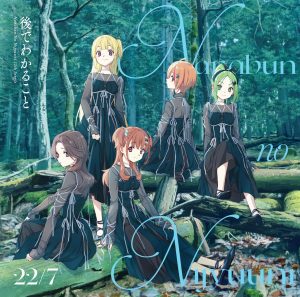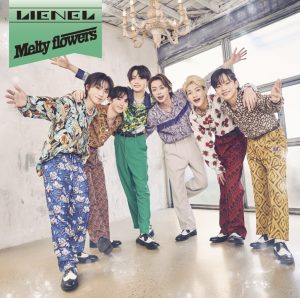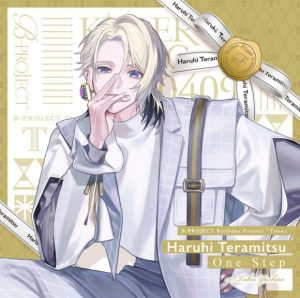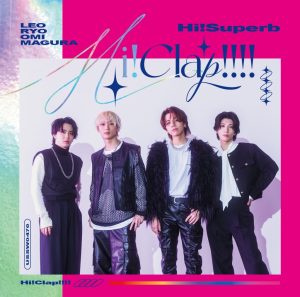Здравствуйте!
このコラムを読んで下さっている皆様、Здравствуйте(ズドラーストヴイチェ)!
英語のアルファベットとは違う、見慣れないこれらの文字はロシア語で、ズドラーストヴイチェは「こんにちは」という意味。
英語のハローと同様、朝昼晩いつでも使える挨拶だ。
何故ここでロシア語かというと、私が物心ついた頃、最初に「こんにちは!」と挨拶を交わした音楽は「ロシア民謡」だった、という事をお伝えしたいからだ。
ロシア民謡と呼ばれるジャンルは、日本民謡の「ソーラン節」などとは違い、様々な時代のポピュラーソングを指す場合が多い。
プロの作詞家、作曲家が創り、歌手が各メディアで歌っている歌である。
「カチューシャ」「ともしび」「カリンカ」「黒い瞳」などのタイトルを挙げれば、学校で習った歌もあるかも知れないし、昭和時代の歌声喫茶を連想する方もおられるだろう。
運動会のBGMに使われる軽快なリズムの歌もあれば、哀愁漂うメロディの、いかにも日本人好みの歌もある。
ロシア民謡との出会いは、私が就学前の子供だった頃に遡る。
当時、母が夜、時々レコードを聞いていた。
ダーク・ダックスが歌う、ロシア民謡のLP盤レコードだった。
日本語の意味さえ分からないのに、ロシア語はもっと分からないが、男性メンバー四人による美しくも大迫力のハーモニーは、幼い私を大いに圧倒した。
歌が恐ろしく聞こえたし、かと言ってその場から逃げられないほど惹き付けられもした。
ある意味、怖いもの見たさに近い感覚だったかも知れない。
お気に入りのレコードを聞く事は、苦労の多かった母の密かな楽しみだった。
母の世界の引き出しを無作法に開けてしまう気がして、子供なりに遠慮していた私は、自分から聞きたいと言い出せず、母が夜レコードを取り出すのを待っていた。
憧れの人が会いに来てくれるのを、今日か明日かと楽しみにしているように。
ロシア民謡から始まった私の音楽への興味は、周囲の影響もあって徐々に唱歌、演歌、アイドル、ロックなどへ広がっていったが、日常の中でふと口ずさむのは、今でもロシア民謡が多い。
原語で歌いたい一心で、学生時代に独学でロシア語を学んだ。
覚えた言葉の大半は忘れてしまったが、何故か歌だけは鮮やかに心に焼き付いている。
家の掃除の時、食器洗いの時、近所を散歩している時でも、気付けば口ずさんでいる。
夜遅く眠気も忘れ、母の傍らで感じていた恐怖と紙一重の強い憧憬が、私の中で小さな炎となって、今もチリチリと燃え続けているのだろう。
過去を振り返ってみれば、いつも音楽と共にあったのだが、当初から作詞家を熱望してきた訳ではなく、むしろ将来の夢は絵を描く方にあった。
就学前から大人になるまで、絵を描く職業に就けないかと真剣に考えていたくらいだ。
しかし、出会ってしまった。
歌詞を書くという、私の人生を方向付けるものに。
出会いの挨拶が聞こえた時、心から作詞と仲良くなりたいと願う自分がいた。
おずおずと手を差し出して握手を求めると、作詞の方も私の手を優しく握り返してくれた。
親しい人々や日常の一コマ、旅先の景色などに心を寄せてみたり、時間や人生といった答えのないテーマにも惹かれたりしながら、ペンを走らせる。
何て楽しいんだ。
絵筆をペンに持ち替えて以来、いつの間にか一切絵を描かなくなっていた。
一方、楽しさの裏に、常に不気味な影がべったり貼り付いている事にも気付いていた。
新たな目標を抱き、明るい未来へ邁進して…という心境に、なかなかなれなかったのである。
絵は好きだったが、才能に恵まれなかった。
私はきっと何も持っていない、他の事をやったって駄目なんじゃないか。
と、未来も可能性も信じられない最悪な思考パターンに囚われて、蟻地獄の穴にずるずる落ちてしまうのである。
相談できる人もなく、一人這い上がったり穴に落ちたりを繰り返し、確かな光を感じられるようになるまで、実に長い時間を要した。
後になって思えば、情熱を傾ける方向を間違えていた上に「ビビっていた」訳だが、何をしたいのか、何を信じたいのか、心が叫ぶものに正直になれずにいたのだ。
しかし、絵を描いてきた経験は決して無駄にはならなかった。
作曲家様から託された作品を聞けば、まず情景が絵として思い浮かぶ。
この世界はどんな色を求めているのか、どんな光と影を塗り重ねればより豊かなものになるのかと試行錯誤する。
一枚の紙に、作曲家様の意図を最大限表現しつつ、一人でも多くのリスナー様が笑顔になれる事を願って、必死で描いていく。
私なりの創造だ。
他人様から見れば、私は不器用で頭の切り替えが遅い人間だろう。
沢山の回り道をして、沢山の経験と挫折を重ねないと目覚められなかった、とんでもない寝坊助作詞家だが、私にとっては必要な道程だったと思う。
そう割り切れた時、ぐずぐずした迷いや劣等感は完全に消滅し、以来クリアな気持ちで真摯に作詞と向き合っている。
私達は出会いの挨拶を日常的に使っている。
挨拶は人に対してだけでなく、花でも動物でも音楽でも、初対面でも親しい間柄でも交わされる。
嬉しさを伴って互いの距離を縮められる時もあれば、不愉快な出来事や手痛い失敗と嫌々近付かなければならない時もある。
出会いとは何かと問えば勿論、人の数だけ定義はあるだろう。
私はただシンプルに、出会いは必然と思っている。
初めてロシア人の友人ができて、Здравствуйте!と挨拶し、彼女と共に思い出深い「カチューシャ」を歌えたのも、きっと必然だ。
自分の人生に必要な存在や出来事だからこそ、出会うし経験する。
多くの場合、そこに善悪はなく、どう受け取るか、無駄にするか教訓にするかも自分次第なのだと思う。
未来を想像するのは楽しい。
作詞コンペの通知を待ちながら、作曲家様は次回どんな素敵な曲を聞かせて下さるだろうかとわくわくし、作品が書き上がれば、皆様がそれをどのように感じて下さるだろうかとそわそわする。
お互い、顔の見えない出会いもある。
だからこそ敬意と親愛を込めて、明るく元気に、私は作品を通して皆様に語り掛ける。
Здравствуйте!
まるちきのこ