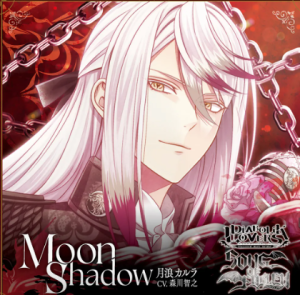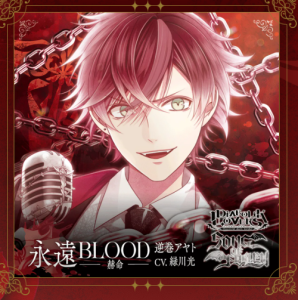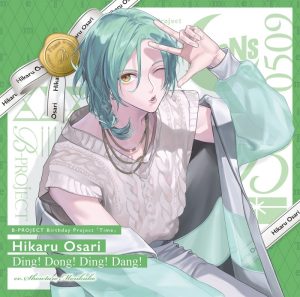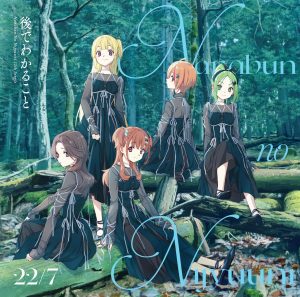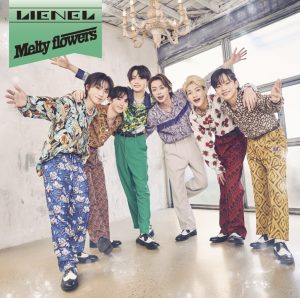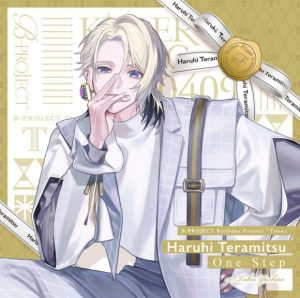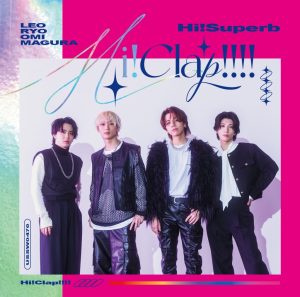10月10日
このところ、ちょっとした体調不良に悩まされてはいたが、今年も10月10日を静かな気持ちで迎える事ができた。
前々回のコラム「8月29日」に続き、「10月10日」とくれば、これが何の日か「廃人(=Laputaファンの呼称)」の皆様にはお分かりだろう。
Laputaのヴォーカリスト、akiの誕生日である。
すっきりしない空模様が何日も続いた中、この日だけは太陽の光が眩しく差し込んで、澄み切った青空が秋らしく、晴れ男と呼ばれたakiらしい日であった。
彼が健在なら、今年で55歳になる。
時の流れの速さを感じつつ、年を重ねて円熟してゆく歌声をもっと聞きたかったな、とつい感傷的になってしまう。
今回のコラムでも引き続き、どうかLaputaとakiについて触れる事をお許しいただきたい。
私が作詞を学んだ教科書がakiの歌詞であると同時に、10月を迎えて何やら語らずにいられない心境になってしまったのだ。
1993年から2004年までのLaputa在籍時代、作詞の殆どを担当していたakiは、難解な言葉をほぼ使わずに、美しく抽象的な歌詞を書いていた。
ダーク、と自らが称しているだけあって、叶わぬ恋や人の世の悲しみなど、ともすればネガティブに感じられる世界を描く事が多かった。
Laputaを知った頃の私は、今で言うパワハラなど人間関係の軋轢や、人生の理想と現実の落差に打ちひしがれていた事もあり、そのダークな世界に身を置くのが心地良かった。
物事が上手くいかなかった時や悲しみに暮れている時、そのダークさが私の闇を否定せず、共感してくれるように思えて大いに救われた。
Laputaがそうだったからでもあるが、当時の私は抽象的な歌詞を好んで聞いていた。
抽象的であると、具体的なモノや場面に限定されない分、歌詞の世界をリスナーの想像に任せられる部分が多い。
受け取った歌詞のイメージを心の中で自由にはばたかせるもよし、言葉の意味やストーリーの流れに独自の解釈を加えて咀嚼するもよし、である。
流行のモノにも世の流れにも左右されないという点では、抽象的な歌詞は時を越えても色褪せないのではないか、と思う。
私はそんな世界を教科書にして作詞を学び、自分好みの歌詞を長くアマチュアとして書いてきた。
アマチュアなら、好きな世界を好きなように書けばいいが、多くのリスナーに歌詞を聞いていただく作詞家という立場になると、状況が違ってくる。
抽象的な歌詞が好きだから、書きたいからといって、作詞家として通用する訳でないのを、後々私は痛感する事になる。
もっとも、作詞家への道を辿る未来がやって来ようとは、その頃想像すらしていなかったのだが…。
対照的に、具体的なシチュエーションが描かれた歌詞ではどうだろうか。
聞いてパッと風景が頭の中に飛び込んできた、まさにそれだという感覚や感情を言い当てられた、新しい価値観に遭遇した、などの経験をなさった方は多いだろう。
中には、作品中のシチュエーションがご自身の経験に重なって、これは私の為の歌なんじゃないか、と心震える思いをした方もおられるかも知れない。
目に見えるような形で提示されれば、リスナーがその世界に断然入りやすくなる。
分かりやすさはリスナーにとって大切で、書き手にとっては作品に興味や愛着を持っていただけるきっかけになるだろう。
それから、自身の好みを超えて新たな書き方を学ぼうという、私の闘いが始まった。
いかに自然に、場面が目に浮かぶように、リスナーの年齢や性別によっても変わるリアルな世界を、時には「あるある」を盛り込んで創るかを考えるのだ。
仮に、中高生リスナーを対象としたラブソングの募集があったとして、自身の初恋などを思い出語りするのはNGだ。
時代を令和に合わせ、令和の中高生のリアルを模索しなければならず、そうでないと古臭く感じられたり、大人が子供に何か言っているように聞こえてしまったりする。
歌う方の事を考えた上で、その世界その年代で生きる人が何を思うか、隣や斜め上から見たらどう見えるかなど、様々に自分の立ち位置を変えてみる。
難解でありながら楽しくもある作業だ。
作詞コンペでは、様々なタイプの作品を求められる。
具体的、抽象的、どのような世界を求められたとしても対応できるだけの力が必要だし、どちらも書けないと太刀打ちできない、というのが現在の私の正直な感想である。
先程はakiの書く歌詞は美しく抽象的で、という話をさせていただいたが、抽象的な中にもハッとするような、赤裸々な思いを綴ったフレーズも多数ある。
一例として、2019年発売のソロアルバム「GREED」に収録された「SEED SONG」をご紹介させていただきたい(「GREED」はインディーズ盤の為、馴染みのない方が多いと思うが、どうかご容赦を)。
「SEED SONG」を今聞き返すと、aki自身の将来を暗示するかのような意味深な作品に思えるが、特筆すべきはそのサビだ。
そう長くないサビのフレーズの中に、akiの人生観、絶望、希望、ヴォーカリストとしての矜持が全部詰まっている。
初めてその作品を聞いた時、リスナーとしての私は肌が粟立つような凄みに圧倒され、作詞家としての私は「やられた!」と地団太を踏んだのである。
決してakiと競いたいのではなく、他のアーティストの創作であっても同じで、素晴らしい作品に出会うと、感動するのと同時に何やら悔しくなってくるのである。
こんなにも人の心を捉えるフレーズを、どうして私は生み出せていないんだ?
答えは簡単、まだまだ修行が足りないのである。
作詞家への道を歩もうと決めた頃から、感性を鍛えたくて、自身の好む作品だけでなく幅広いジャンルを聞くようになった。
そして、素晴らしい作品に出会う度に「やられた!」と苦悶にのたうち回るのである。
「芸術家は上には上がいると知っているから、傲慢にはなれないよ」と、或る音楽業界の先輩から聞いた話があり、まさにその通りだと思っている。
傲慢になどなった事はないし、なれる訳がない。
じたばたしながら学んで、少しずつでも進むしかない。
日々勉強である。
まるちきのこ