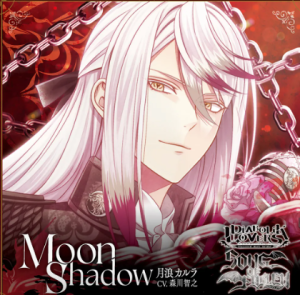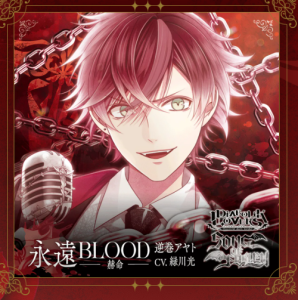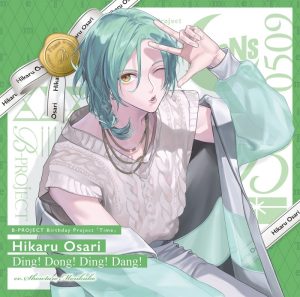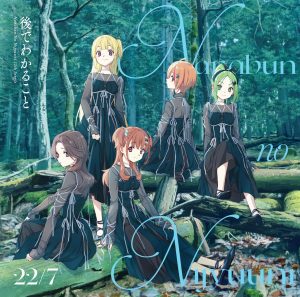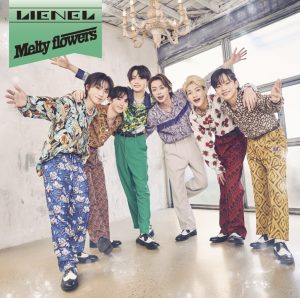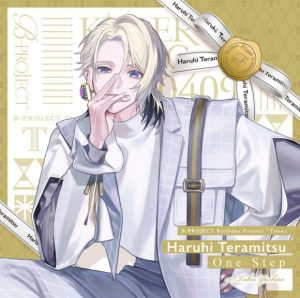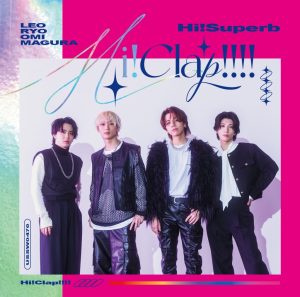Aメロ
作詞をするうえで、どこから書き始めるのかは人それぞれだと思う。
私の場合は、Aメロ→Bメロ→サビという順序を追うスタイルがしっくりきている。というか、その書き方が好きなのである。もちろん、その前に「今日のごはんは和食かな?洋食かな?」くらいの、ざっくりしたテーマは決めている。
書き始める前に、とにかく何回も音源を聴く。最初は何も浮かばないことも多いけれど、繰り返し聴くことで少しずつ曲の輪郭が見えてくる。同じ部分を何回もリピートして、「あ、ここはこういう感情が合うな」「このフレーズはこう繋げたいな」と思える瞬間を探すのが、私にとって一番楽しい時間だ。すぐに歌詞が湧いてくるときもあれば、考えても全然出てこないときもある。それでも、とにかく音源を聴き込むことから私の作詞は始まる。頭の中ではなんとなく「こういうサビにしよう」というイメージを浮かべて、サビの決め手となるワンフレーズがはっきりしたかな?くらいでAメロから書いていく。
セオリー通りならば、サビから書くのが上手な作詞の方法だということは理解しているし、サビ始まりの曲ならサビから書いている。何度もデモ音源を聴き、そのメロディーにハマる物語を想像することが、作詞をするうえでいちばん好きな時間だったりする。
Aメロは、たとえるならメニュー表を開いて、どれにしようかワクワクしている感覚。Bメロは注文して料理を待っているときの期待感、サビは「いただきます!」と出来上がった料理を食べている至福の時間。そんな感覚に近いのかもしれない。だから私にとって、Aメロこそ一番大切に作っていきたいパートだ。
作詞を料理に例えると、メロディーは食材、言葉は調味料だ。どんなにいいフレーズでも、メロディーとの相性が悪ければ美味しい料理にはならない。例えば、お刺身にバニラアイスをのせることを想像してみると、挑戦的ではあるが多くの場合美味しくなるとは思えない。奇跡的に合う組み合わせもあるかもしれないが、やみくもに合わせても完成度の高い料理にはならない。だからまた今日も、メロディーを何度も聴き、曲の空気感に合う言葉を探す。
料理も下ごしらえを怠ると味が決まらないように、Aメロは曲全体の雰囲気を決める“下ごしらえ”のようなものだ。野菜を切る大きさを揃えるだけで料理の見栄えや食感が変わるように、Aメロの言葉選びひとつで曲の印象は大きく変わる。ここを丁寧に整えておけば、その後の展開も自然に繋がっていく気がする。
作詞の締切があると、他に悩みや嫌なことがあっても、それを忘れさせてくれるくらいに頭の中の大部分はコンペの曲のことでいっぱいになる。お風呂の中や洗い物をしているとき、移動中など、ふとした瞬間に言葉が浮かぶことも多い。
よく「いいフレーズはメモしなさい」と言われるが、私はあまりメモをしない。本当に残したい言葉は、書かなくても忘れないと思っているからだ。逆に「このフレーズをどうしても使いたい」と強く思いすぎると、メロディーに合わなくても無理にねじ込んでしまうことがある。そして大体失敗に終わるのである。それよりも、いちばん大切なのは曲に寄り添った自然な言葉を見つけることだと感じている。
そのせいなのか、作詞先行で音源がないコンペになると途端に書けなくなってしまう。自分で適当なメロディーを考えながら書くようにしているが、音源があるときと感覚がまるで違うのだ。これはもしかしたら、日頃からメモを取らない私の悪い癖が影響しているのかもしれない…。作詞先行のコンペのときは、セオリー通りサビから書いていることのほうが多い。メロディーありのコンペは、デートに着ていく服をウキウキ迷っている感覚で、メロディーなしの作詞先行のコンペは、好きな相手とタイミングが合わず、なかなか会えなくてモヤモヤしている感覚に近い気がする…。
私の作詞人生のイントロは、音楽を好きになった瞬間。では、Aメロ地点はどこだったのだろうか?
小学生の頃、流行りの曲で替え歌を作ったりするのが好きだった。ピアノの練習曲に勝手に歌詞を当てて遊んでいた時間もそうだったんだろうなと思う。ブルグミュラーの「貴婦人の乗馬」を弾きながら、
♪パッカ パッカ お馬がはしーる
きっふじん 乗せて行くーよっ♪
と心の中で歌っていた。そんなふうに音楽に自然と言葉を乗せて遊ぶことが、私にとっての作詞の入り口だったんだろう。あの頃のワクワクした気持ちは、今でも私の中に残っていて、作詞をするときの原動力になっている。
誰でも一度は替え歌を作ったことがあるのではないだろうか?子どもの頃のそういう純粋な気持ちを持ってメロディーを聴けば、自然と歌詞が浮かんでくる気がする。作詞の本質は、そこにあるのかもしれない。
もちろん「サビが大事」なのは間違いない。でも、個人的にはAメロも同じくらい重要だと思っている。
例えば、中森明菜の「十戒」は思わず聴き入りたくなる強烈な一言で始まり、一気に引き込まれる。Adoの「うっせぇわ」も、冒頭のフレーズから世界観が強く伝わる。私が大好きなアニメの「創聖のアクエリオン」やマクロスFの「ライオン」も、どうやってこんな言葉にたどり着くんだろう?と思うような素敵なフレーズで始まるし、小さい頃夢中になったセーラームーンの「ムーンライト伝説」も、少し切ないフレーズから始まるAメロで耳を惹きつけられる。
最近だと、サカナクションの「怪獣」はサビ始まりと思わせてそうじゃない構成で度肝を抜かれたし、M!LKの「いいじゃん」はSNSでサビだけ知っていて、初めてフルで聴いたときにAメロとのギャップに拍子抜けしたけれど、作詞だけで見ると違和感もなくすんなりと受け入れられる。こうした冒頭の一言に強い力を持つ楽曲は、間違いなく最後まで聴いてもらえる曲になるのだと思う。
作詞のやり方は人の数だけあっていいし、どれも間違いではない。サビから書くのも正解だし、タイトルやテーマから世界を作るのも正解だ。どのやり方も、その人にとっての正解になると思う。ただ、もしこの文章を読んでくれた誰かが「作詞をやってみたい」と思ったら、私はこう伝えたい。
何度もメロディーを聴くこと。そして、Aメロも大事にすること。
曲の最初の一歩を丁寧に仕込めば、その歌は最後まで自然に完成していくと思う。私はこれからも、メロディーに寄り添いながら、自分に合ったやり方で作詞を続けていきたい。そして、誰かを惹きつけられるAメロのフレーズを見つけたい。こんな偉そうなことを言えるような立場ではないけれど…。
それでは、Bメロ編に続く!